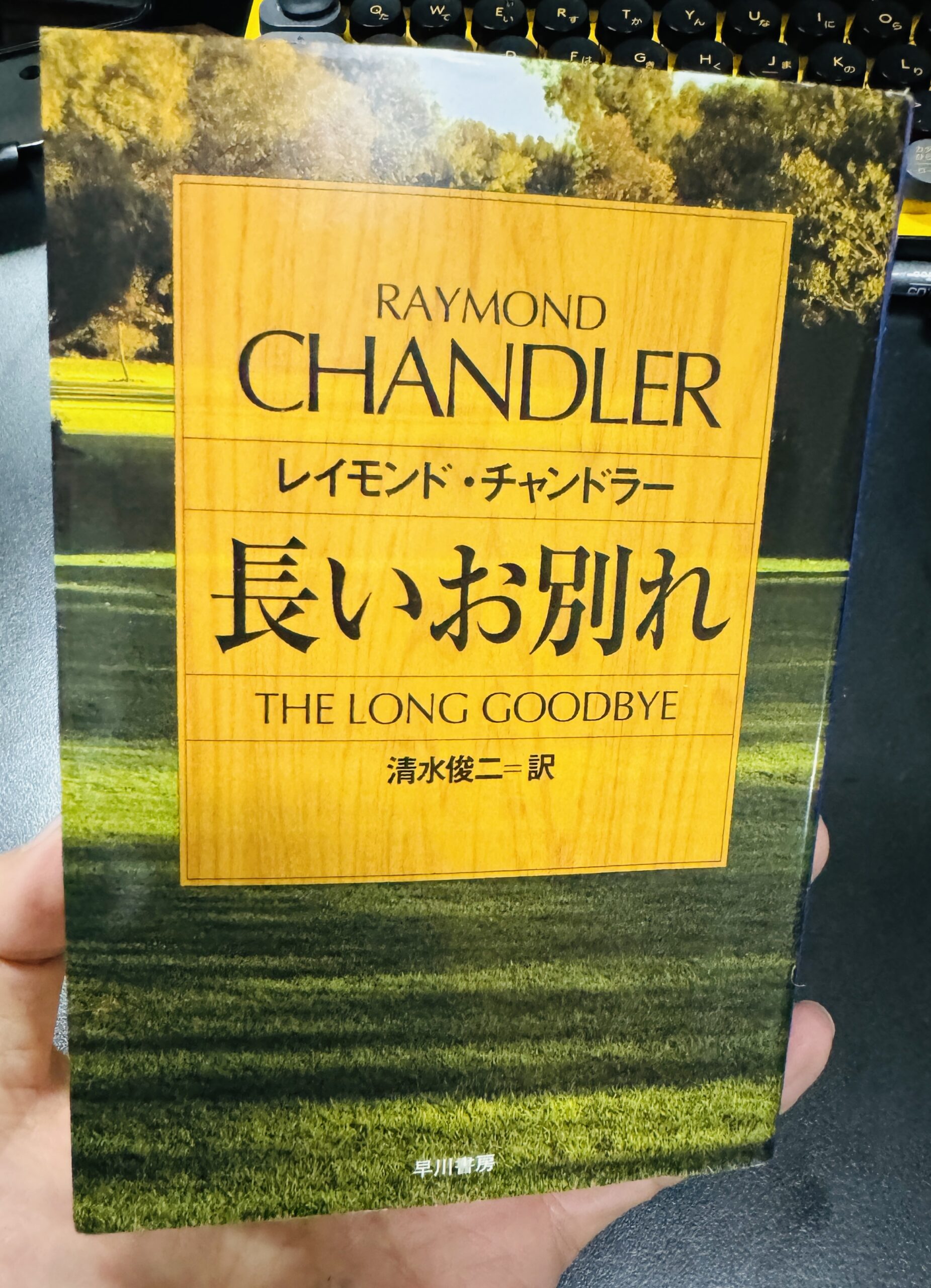レイモンド・チャンドラーの最高作品『長いお別れ』(THE LONG GOODBYE, Raymond Chandler, 1953)を初めて読んだのは、30年程前であったと記憶している。私は主人公である探偵、フィリップ・マーロウの精神に憧れ、彼の気概を真似した結果、良くも悪くも、マーロウが今の自分を形成していたと、本作品を再読して再認識した。
フィリップ・マーロウは、タフで、権力や暴力に物おじせず、センチメンタルでロマン主義である。自分の信念を曲げず、緻密な調査と人的ネットワークを駆使して、依頼人の問題を解決する。マーロウのセリフの一つ一つが緻密で、ウィットに富んでおり、時々わざと人を不快にさせる。
本作品を再読して驚いたことは、本作品におけるマーロウの年齢は42歳で、私より若かったことだ。初めて本作品を読んだ時はもちろん、彼よりも若かったのであるが、こうして再読してみると、月日の流れる速さを、感じざるを得ない。本作品において、マーロウは永遠に42歳であり、『サザエさん』と構造は変わりない。
マーロウの探偵家業は、決してコストパフォーマンスの良い仕事ではなく、お金もそれほど稼げていない。独身で、酒とチェス(一人で本を読みながら行うチェス)が好きで、あちらこちらを車で走り回っている。
振り返ると、私もマーロウの生き方をなぞらえてきて、独身ではないものの、つまらない事にこだわって、人を怒らせ、痛めつけられたり、損してきたのかもしれない。風に流されることを嫌い、川の流れに逆らい、余計なエネルギーを使ってきたと思う。
この小説に出てくる、テリー・レノックスが好んで飲んだギムレットを自分で作ってみたくなり、サントリーのドライジンと、サントリーのライムジュースをステアして(時にはシェイクして)、それっぽいギムレットを作ってみたり、バーでギムレットを作ってもらったが、小説の中で擬似体験したギムレットは飲めなかった記憶がある。推測するに、ローズのライムジュースはとても甘く、ジンは、ゴードンのドライジンではないかと思う。甘ったるさと、ジンの中では最もドライと思われるゴードンのジンを微妙な感じでステアしたカクテルは、アメリカ西海岸側の、ジリジリした暑さと、バーの中のヒヤリとした空気に合っている気がする。
のちに私は、ロバート・B・パーカーが編み出した新しいハードボイルド小説シリーズである、スペンサーなる探偵が活躍する小説に没入して、その頃には、内藤陳なるコメディアンが推奨する小説に没入して、彼が主催する、「深夜プラス1」なる酒場に一度だけ入り、とても居心地の悪い思いをしたことを思い出す。「深夜プラス1」はおそらく、新宿ゴールデン街にはもう無いであろう。

マーロウはおそらくイケメンな中年男であろう。レイモンド・チャンドラーの著者近影を見る限りは、著者はあまりモテなかったので、理想の男性を作り上げたのだと思う。私もマーロウのような男になりたいと思い、半分はよかったと思い、残りは後悔している。